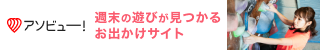仮想通貨の基礎|USDTって何?なぜ皆が使うの?(送金と手数料の実務つき)
USDTとは
米ドルに連動(1USDT ≒ 1USD)するステーブルコイン
発行体は Tether。発行体は準備資産(米国債・現金等)を保有し、発行残高に対する四半期のアテステーション(外部確認報告)を公開している。
最大規模のステーブルコイン
対法定通貨の“待機資金”や取引用の基軸として広く使われる(取引ペアが豊富で流動性が厚い)。Tether はサポートするブロックチェーンの見直しを随時行っている。
USDTは“同じ1USDT”でも複数のチェーンに存在する
代表例:ERC20(Ethereum)、TRC20(TRON)、ほか複数。発行体は「どのチェーンでも1 USDTは1 USDT」という扱いだが、アドレス形式・手数料・必要なガス(後述)が違う。送金時はチェーンを必ず一致させること。
重要:送金元がERC20なら受取先もERC20。TRC20→TRC20。同じ“USDT”でもチェーンを跨いだ直接送金は不可(ブリッジ等が必要)。
送金の仕組みと“ガス代”
ブロックチェーン上の送金は、ネットワーク手数料(ガス)をそのチェーンの“ネイティブ通貨”で払います。
- ERC20のUSDT送金 → ガスは ETH が必要。
- TRC20のUSDT送金 → ガスは TRX が必要(TRONでは“帯域/エナジー”というリソースを消費。アカウント未アクティベートの場合は初回に余分なコスト)。
実務の感覚
ERC20:ネットワーク混雑時は手数料が高止まりしやすい。
TRC20:一般に安価・高速で送金しやすい(それでもTRX残高ゼロだと送れない)。
どのチェーンを選ぶ?
コスト最優先 → TRC20(TRON)を選ぶ人が多い。
DeFi/NFT・L2活用 → ERC20(Ethereum)側が選ばれやすい。
取引所の対応 → 取引所やウォレットが対応する入出金ネットワークで決める
USDTの“サポートチェーン”は見直しが入る
Tether は2024〜2025年にかけて利用の少ないレガシーチェーンの縮小を発表。Omni / BCH-SLP / Kusama / EOS / Algorand などで新規発行停止→段階的なサポート縮小を進め、2025年8月には凍結は行わず“非サポート(未支援)”扱いに変更するアップデートを公表。最新の扱いは公式“News/Transparency”で確認を。
リスクとリテラシー(初心者が最初に知っておくべきこと)
- 発行体リスク(中央集権)
発行体は、法執行機関の要請等により特定のアドレス凍結を行った事例がある(例:制裁対象との関連や事件対応)。 - ペッグ変動リスク
市場ストレス時に一時的に1ドルから乖離することがある。基本は裁定取引と償還で戻る設計だが、短期の価格変動はゼロではない(相場状況次第)。Tether は四半期アテステーションと準備内訳を公開している。 - ネットワーク選択ミス
ERC20宛にTRC20を送る等のチェーン取り違えは、原則自己責任で資産喪失に繋がる。入金画面のネットワーク名とアドレス接頭(0x… / T…など)を必ず照合。
実務チェックリスト(失敗しない3ステップ)
- ネットワークを合わせる:送金元と受取先のERC20 / TRC20を確認。先に受取側の“入金ネットワーク”を選び、アドレスを取得。
- ガスを用意:ERC20ならETH、TRC20ならTRXを少額で常備。ゼロだと送れない。
- 少額テスト送金:初回は少額→着金確認→本送金。取引所の出金手数料も事前にヘルプで確認。
まとめ
USDTは、価格安定・流動性・対応取引所の多さで“クリプトの共通語”になっています。
一方で、チェーンの違いとガス通貨を理解していないと、送れない/届かないという初歩ミスに直結します。
「ネットワーク一致」「ガス常備」「少額テスト」
――この3つを徹底すれば、USDT送金は“日常の道具”として機能します。